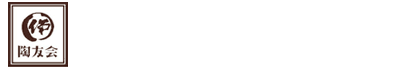-
-
[山本 雄一先生]
文化財の先生方の特別講座にて、山本雄一先生のお宅へ伺いました。
ご自宅にある応接室に通して頂き、お話をして頂いたのちにお茶室と工房を見学いたしました。
茶陶ははずせないとおっしゃっていた先生は、茶道を知らずに茶碗を作るという事は、短距離選手が幅跳びをするのと同じことだとごもっともだと感じることをおっしゃって下さいました。
何事も使う人の事を考え作らなければならないという基本を学んだように思います。
窯場の隣にある、秘密の部屋を見せてあげると言いながら開いた扉の向こうにはものすごい数のドリルやルーター、それから自ら作られたというセンサーや制御装置などなど、機械がずらっと... [read more]
-
-
[研修生募集]
H27年度下期コースの研修生を募集しています。
備前焼を学びたい方、ご興味のある方は備前陶芸センターのホームページをご覧下さい。
http://bizen-tougei.okayama.co/
6ヶ月コースの他に1ヶ月コースもあります。
⇒ 記事を読む
※facebookページより... [read more]
-
-
[石膏型つくり]
鈴木黄弌先生の石膏型の授業で、皆、思い思いの原型で石膏をとりました。
見本で見せて頂いた猿の置物を抜く手慣れた先生の動きは非常に早く、あっという間に1匹の猿が生まれました。
原型を埋没するように粘土で囲い土手をつくり、石膏がある程度混ざったらそこへ流し込む・・・
の繰り返しです。
早めに土手をはずし、石膏が固まらないうちにまあるく仕上げます。ケーキのクリームのような感じです。
両面とって出来上がり。
あとは、合わせ面に土の逃げ場になる溝を掘り出来上がりです。
ひとつひとつの作業が後の型抜き作業を左右させるのだと思います。http://www.facebook.com/... [read more]
-
-
[人間国宝 伊勢﨑 淳先生]
先日、国指定重要無形文化財保持者である伊勢﨑淳先生の工房見学に伺いました。
まず、緊張気味な研修生からなぜ備前焼の研修に参加したのかなど自己紹介からはじまり、その後縄文土器・弥生土器・須恵器などやきものの歴史と備前焼のルーツ、先生が備前焼を始められた頃のお話をして下さいました。
備前焼の歴史も1000年近いと言われていますが、それより遥か昔からやきものの技術はかなり出来上がっていたということで・・・そんな大昔からすでに焼物を割れにくくするために焼成後の破片を粘土に混ぜて焚いて強度を増したり、熱効率をあげるための窯の開発などがなされていた事など
先生は、備前高校... [read more]
-
-
[備前焼小町…備前焼研修]
今年の備前焼小町が決定し、備前焼をPRするための知識を深めるべく備前陶芸センターで研修されました。
昨年に引き続き、第28代備前焼小町の荒木詩乃さんと今年の第29代 石原茉依さんです。
吉本正先生と藤田龍峰先生より指導を受けながら、備前焼がどういう工程で作られているのか学んでもらいました。
2人はそれぞれ、たたき皿や手びねりの花入、さる?ねずみ?兼用のかわいい動物やモアイ像など制作しました。
実際に土を触り備前焼をより身近に感じていただければと思います。これからPR活動が始まっていくと思いますが、2人のかわいい笑顔とともに備前焼を広く宣伝していただきたいな、と思... [read more]
-
-
[茶道]
高坂 弘先生による茶道の講座を学びに行きました。
先生は、以前岡山県立備前高等学校(現岡山県立備前緑陽高等学校)の窯業科の教師として指導もされていた方で、化学的視点や備前焼・茶道の歴史など様々な分野でご指導いただける先生です。
この度は、表千家の茶道の講座を開講して頂きました。
茶道には、礼儀作法や茶器の心得など多く学ぶべきことが詰まっています。ので、数時間で詳細は学べないのですが、この日はお茶のいただき方・たて方・道具や名称などをご説明頂きました。
慣れない正座、半畳三歩で歩く、座り方や方向転換・・・
ロボットの動きになりながらようやくお抹茶をいただく。
事細かに... [read more]
-
-
[宝瓶制作]
鈴木黄弌先生に宝瓶作りの授業をして頂きました。
宝瓶は取っ手のない急須で、昔はコーヒーなどではなく宝瓶で煎茶器に入れたお茶をお客さんに振る舞っていたそうですが、今は使う人も少なくなっているそうです。
普段は2日かけて穴を開けたりしているそうですが、この日は気温30℃を超える暑さの中、扇風機の風と気温でどんどん土が乾いていき、数時間中にみんなで黙々と宝瓶をつくりました。
径や口、横から見た形など、バランスが難しいです。
水キレをよくするためのヘラ使いなど、ポイントも教えて頂きました。
ロクロとはまた違う難しさと面白さがあり、手びねりの作品はひとつひとつに時間をかけ形を整えて... [read more]
-
-
[窯焚き見学]
陶芸センターの講師、藤田龍峰先生の息子さん藤田昌宏さんが窯を焚かれるという事でお忙しい中窯焚き見学させていただきました。
先生の登り窯は初代藤田龍峰さんのころに築き、修復や改修を経て現在100年ほどの歴史をもつ窯だそうです。
そんな年月が経ったとは思えない程立派な煙突が真上にドンと伸びており、うっすらと煙が舞ってその時点で温度は800℃を超えたところでした。
藤田先生の窯は伊部の街道沿いの、家と窯のひしめく場所にあり、近隣にもたくさんの備前焼窯元とたくさんの煙突が伸びています。この光景を目の当たりにすると改めてやきもの産地、備前のすごさを感じます。
親子で同じ窯に詰め、焚... [read more]
-
-
[山本 出先生]
文化財の先生方の特別講座にて、この度は山本出先生の元へ伺いました。
ギャラリーで作品を拝見したり、先生の作品が掲載されている本や写真などを踏まえてお話をして頂きました。
彫塑で学ばれた技術を備前焼で表現され、人体の細胞や自然の物からインスピレーションを受け作陶されていらっしゃるそうです。
その後、先生がフランスの地で現地の土と窯で作品制作した様子(NHKの密着取材で放送された番組)を見せて頂きましが、1ヶ月の限られた時間の中で現地の土を使い、始めて焼く円筒系の窯で窯焚きをするという内容でした。
土は非常に固く手首を痛めながらも通常の倍の時間をかけて練り、自分たちで薪を割... [read more]
-
-
[山陽新聞掲載]
5月7日(木)山陽新聞の夕刊に、備前陶芸センターの記事がテレビ欄の下8面に大きく大きく掲載されました!
平成27年上期コース開始の日に山陽新聞文化部の記者さんが研修生に混じり、菊練りの体験をされた時のものです。
備前焼の魅力や面白さと難しさ。。それから備前陶芸センターの後継者育成事業や体験プログラムの要項など、多くの方へのPRになることを期待します。http://www.facebook.com/pages/p/222662734610619... [read more]
-
-
[窯跡探索]
備前市伊部には、国指定史跡備前陶器窯跡があり発掘調査された窯跡も多く点在しています
今回研修生と卒業生で窯跡の探索に行きました
山土の堆積を見たり穴窯の鎌倉時代の合が淵や南北朝時代のグイビが谷の窯跡を見学したそうです
窯跡には陶片がゴロゴロ転がっていて、甕や擂鉢の口づくりなどを見ればいつ頃の時代に焼かれたものかわかりますhttp://www.facebook.com/pages/p/222662734610619... [read more]
-
-
[特別授業 講義]
備前焼伝統産業会館にて延原勝志先生による講義が開講されました。
内容は、胎土からみたやきもの・温度による変化・窯の構造・備前焼の歴史などです。
一般陶芸についてご存知の方も初めての方も、目には見えない化学的な物質の変化、想像が広がる伊部一帯の過去の風景など、興味深いお話で勉強になったかと思います。http://www.facebook.com/pages/p/222662734610619... [read more]